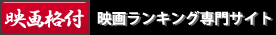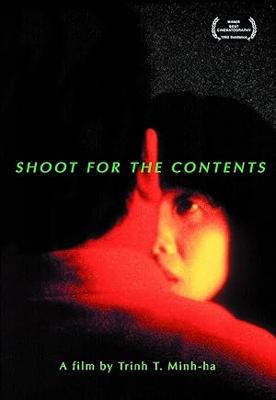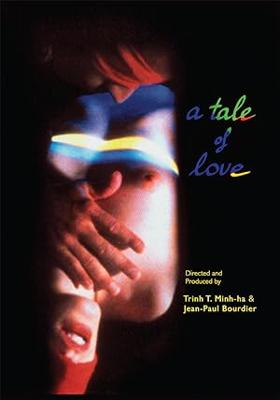スポンサーリンクあり
全5作品。トリン・T・ミンハ監督が制作した映画ランキング
-
西アフリカ・セネガルの女性たちの日常。語るのではなく、ただ映し出すことで、観る者の視線を問い直す映像詩。
舞台は西アフリカ、セネガル共和国の農村地帯。そこに暮らす女性たちの、ありのままの日常風景。水汲み、炊事、子育て、そして談笑。カメラは解説や解釈を一切加えず、ただ静かに彼女たちの姿を捉え続ける。断片的に挿入される監督自身の声は、西洋的なドキュメンタリー手法そのものへの批評。これは異文化を「語る」ことの暴力性を告発し、観る者に「どのように見るか」を突きつける、挑戦的な映像体験。文化人類学の常識を覆す、前衛的ドキュメンタリー。ネット上の声
- 目に見える全てのものごとを記号として理解してしまいがちな私たちへの反省を促す映画
- 何も示さないように撮る、っていう不可能なことを必死でやろうとしている
- 見ることは見られることである、というドキュメンタリストとしての意識
- 製作当時セネガルで音楽を教えていたトリン・T・ミンハによる映像作品
ドキュメンタリー- 製作年1982年
- 製作国アメリカ
- 時間40分
- 監督トリン・T・ミンハ
- 主演---
-
男尊女卑社会であるヴェトナムにおける女性史を綴ったドキュメンタリー。監督・構成・編集・翻訳はトリン・T・ミンハ。ヴェトナムにおける女性の抵抗の歴史、その民衆史に描かれた口承伝統、マス・メディアのイメージなどを通して、ヴェトナムと文化の様相を描いている。 ポスト・フェミニズム、ポスト・コロニアリズム(植民地主義)の第一人者にして女流映画作家のトリン・T・ミンハ(53年ベトナム、ハノイ生)作品の特集で上映された。東京写真美術館で開催された現代女性作家展『ジェンダー/記憶の淵から』(1996年9月5日~10月27日)関連企画で、新しい試みとして写真と映画が同一枠で展覧・上映された。
ネット上の声
- 新美で寝ぼけながら見た 唄が良すぎて内容を全く覚えてないのだ かなりアートフィル
- ヴェトナム出身で、アメリカで活動している詩人でドキュメンタリー映画作家のトリン・
- 時間の都合で最後20分は不完全燃焼なんだけれど、そこまで観た感想としてまずフェミ
- 撮り方がゴダールっぽくて、フランス元植民地ベトナムのエリートらしいと思った
ドキュメンタリー- 製作年1989年
- 製作国アメリカ
- 時間108分
- 監督トリン・T・ミンハ
- 主演---
-
3
核心を撃て
89年6月3日の天安門事件後の中国に取材し、かの国の政治と文化について考察したドキュメンタリー。監督・脚本・編集はトリン・T・ミンハ。出演は呉天明ほか。 ポスト・フェミニズム、ポスト・コロニアリズム(植民地主義)の第一人者にして女流映画作家のトリン・T・ミンハ(53年ベトナム、ハノイ生)作品の特集で上映された。東京写真美術館で開催された現代女性作家展『ジェンダー/記憶の淵から』('96年9月5日~10月27日)関連企画で、新しい試みとして写真と映画が同一枠で展覧・上映された。ドキュメンタリー- 製作年1991年
- 製作国アメリカ
- 時間102分
- 監督トリン・T・ミンハ
- 主演---
-
4
愛のお話
“愛”を探究する女について語りながら、いわゆるラヴ・ストーリーにおける性と心の遊離の問題を問いかけた一編。19世紀初頭に書かれたヴェトナムの国民的な愛の詩歌『キュウのお話』を基に、家族のために娼婦となっておのれの“性”を犠牲にした女の物語を現代アメリカに置き換えて映画化。監督・撮影・脚本・編集はトリン・T・ミンハ。製作はエリカ・マーカス、音楽はコンストラクション・オブ・ルインズ、使用写真はキャサリン・ビーレがそれぞれ担当。出演はマイ・ヒュン、ジュリエット・チェン、ドミニク・オーヴァーストリート、キュウ・ロアンほか。ポスト・フェミニズム、ポスト・コロニアリズム(植民地主義)の第一人者にして女流映画作家のトリン・T・ミンハ(53年ベトナム、ハノイ生)作品の特集で上映された。東京写真美術館で開催された現代女性作家展『ジェンダー/記憶の淵から』('96年9月5日~10月27日)関連企画で、新しい試みとして写真と映画が同一枠で展覧・上映された。ヒューマンドラマ- 製作年1995年
- 製作国アメリカ
- 時間108分
- 監督トリン・T・ミンハ
- 主演マイ・フィン
-
5
ありのままの場所
ドキュメンタリー- 製作年1985年
- 製作国アメリカ
- 時間102分
- 監督トリン・T・ミンハ
- 主演---
ジャンル別のランキング
ここがダメ!こうしてほしい!
どんな些細なことでも構いません。
当サイトへのご意見を是非お聞かせください。
 貴重なご意見ありがとうございました。
貴重なご意見ありがとうございました。
頂いたご意見を元に、価値あるサイトを目指して改善いたします。 送信に失敗しました。
どんな些細なことでも構いません。
当サイトへのご意見を是非お聞かせください。
頂いたご意見を元に、価値あるサイトを目指して改善いたします。 送信に失敗しました。